フリーランスとして独立を考えるときに、不安に思うのが 「保険・年金・社会保障はどうなるの?」 という点ではないでしょうか。
会社員であれば自動的に加入していた制度も、フリーランスになると自分で手続きを行い、負担する必要があります。
今回は、フリーランスエンジニアが知っておくべき「保険・年金・社会保障」の仕組みを、会社員との違いも交えて解説します。
健康保険|国民健康保険と任意継続の選択肢
私が会社員のときは、勤務先の健康保険組合や協会けんぽに加入していました。
ですが、フリーランスになると、一般的には 国民健康保険 に加入することになります。
ただし、条件を満たせば 任意継続制度 を利用し、会社員時代の健康保険を最長2年間は継続可能です。
- 国民健康保険:所得によって保険料が変わる
- 任意継続:前職の標準報酬月額を基準に保険料が計算される
フリーランスの所得が多い場合は、任意継続制度を利用したほうがお得になります。どちらが得になるかは収入や家族構成によって異なるため、シミュレーションして検討すると良いでしょう。
年金|厚生年金から国民年金へ
会社員のときは「厚生年金」に加入していましたが、フリーランスは 国民年金 のみとなります。
これにより将来受け取れる年金額は減ってしまうため、以下のような対策を検討することが有効的です。
- 国民年金基金:自営業者向けに年金を上乗せできる制度
- iDeCo(個人型確定拠出年金):節税しながら将来の年金を積み立てる仕組み
「老後資金は自分で準備する」という意識が必要です。ただし、上記については、デメリットもあるため、出口戦略を考える必要があります。
出口戦略については今後、別の記事でご紹介させて頂く予定です。
雇用保険や傷病手当金はどうなる?
会社員の大きな安心材料である「雇用保険」や「傷病手当金」ですが、フリーランスになると基本的には対象外です。
- 失業手当 → なし
- 傷病手当金 → なし(ただし、退職時に条件を満たし任意継続している場合は利用可能な場合あり)
※利用には諸条件があるため、ご自身の健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。
代わりにフリーランスは以下のような準備が大切です。
- 所得補償保険:病気やケガで働けなくなったときの収入をカバー
- 民間の医療保険:高額医療費がかかったときの備え
保険に入ることで心の安心につながりますが、ご自身の状況に合わない保険に加入すると、無駄な出費になってしまう可能性もあります。本当に必要な保障を見極めることが大切です。
公的な保障や将来への備えも検討しよう
フリーランスが利用できる公的な制度や、将来のための備えには、以下のような選択肢もあります。
- 労災保険の特別加入制度
フリーランスでも、一定条件を満たせば「特別加入制度」によって労災保険に入れる場合があります。万が一の事故や病気で仕事ができなくなった際の備えとして検討できます。 - 小規模企業共済
将来の退職金のように活用できる「小規模企業共済」は、フリーランスに人気の制度です。- 掛金は全額所得控除になり、高い節税効果が期待できます。
- 廃業時や老後に共済金を受け取れます。
- 税金対策と将来の資産形成を両立できるため、ぜひ検討したい制度です。
これらの制度は、万が一の事態だけでなく、将来設計や節税対策としても非常に有効です。ご自身の状況に合わせて、活用を検討してみましょう。
まとめ
会社員とフリーランスの大きな違いは、社会保障の大部分を自分で選び、準備する必要がある という点です。
- 健康保険:国保か任意継続かを選択
- 年金:国民年金+α(iDeCoや基金)で補強
- 雇用保険や傷病手当:基本的になし → 民間保険で備える
- 共済制度:小規模企業共済などで将来に備える
フリーランスになると「自由な働き方」が可能になる一方で、安心を得るには自分で仕組みを作る必要がある ことを意識しましょう。
これから独立を考える方は、案件やスキルだけでなく、「万が一の時にも困らない生活の安心」も同時に準備しておくことをおすすめします。
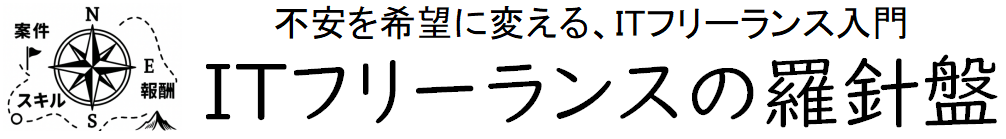
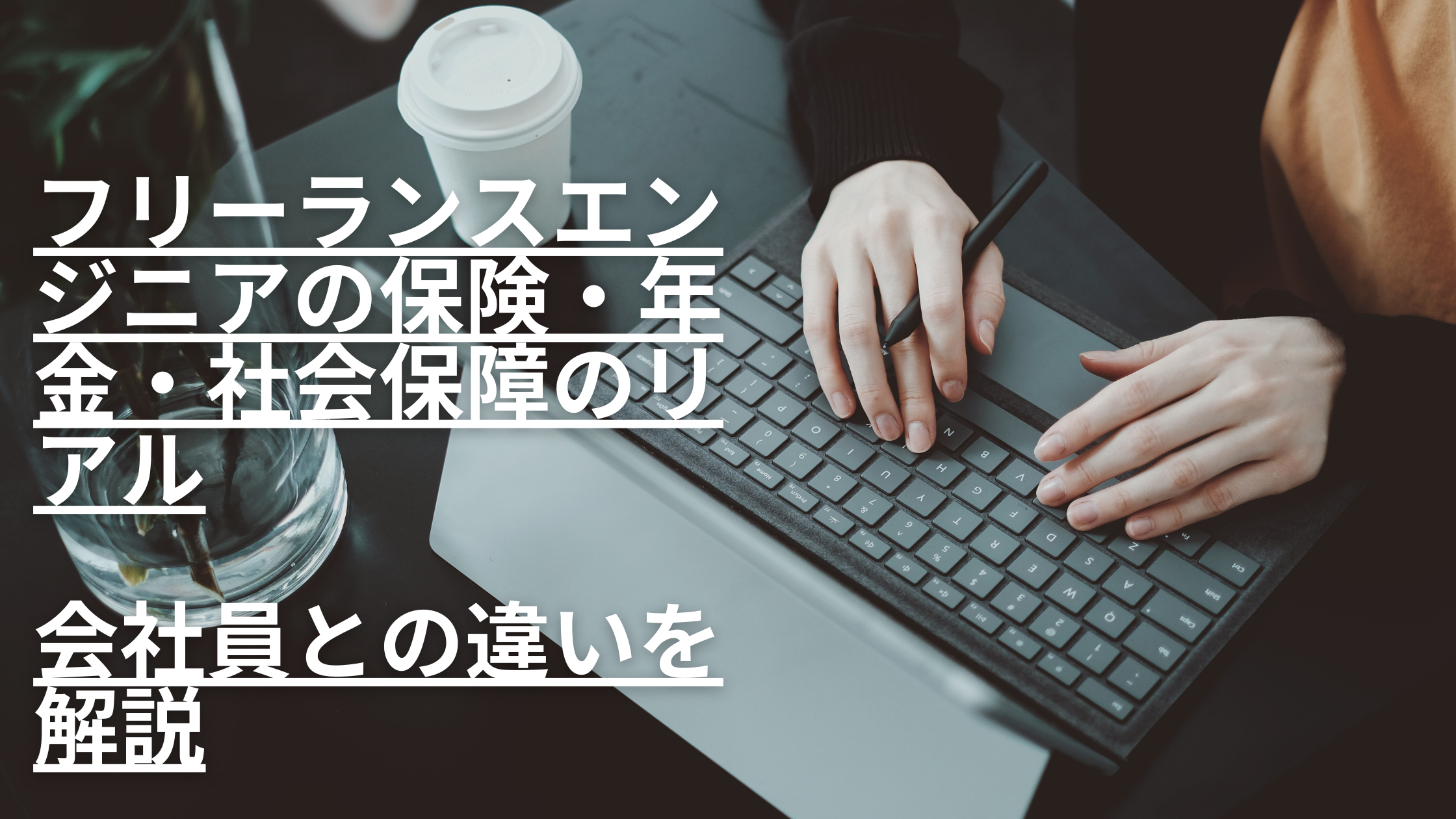
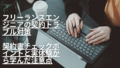

コメント