フリーランスを目指す方の中には、なるべく安定した単価で続けられる案件に携わりたいと考える方もいると思います。
そこで、今回ご紹介したいのがSES契約です。
本記事では、実際にSES契約で働いてきた経験をもとに、メリットやデメリット、案件の実態について詳しくご紹介します。
SES契約とは?
SES(システムエンジニアリングサービス)契約とは、クライアント企業の現場に常駐し、エンジニアの労働時間に応じて報酬が発生する契約形態のことです。
契約形態には以下のような違いがあります。
- 請負契約:成果物に対して報酬が発生する
- 派遣契約:派遣会社が雇用関係を持った上で労働を提供する
- SES契約:労働時間ベースの準委任契約
このように、それぞれの契約形態には特有の特徴があり、自分の働き方やキャリアプランに合わせて選択することが重要です。SES契約は、特に経験を積みたいエンジニアや、収入の安定を求めるフリーランスにとって、魅力的な選択肢となります。
SES契約のメリット
案件が豊富で見つけやすい
SES契約はIT業界で最も普及している契約形態の一つ。
特にインフラ、運用、開発案件においては、フリーランスエージェントを介して多くの案件の紹介を受けることができます。
安定した収入が得やすい
私自身も月単価50万円(税抜)・税込55万円を安定して得られており、正社員時代の収入(18万円)と比べて大きく改善しました。
スキルアップの機会が多い
常駐先で様々なプロジェクトに携わることで、新たな技術や業務フローに触れる機会が増え、キャリア形成が促進されると感じています。
SES契約のデメリット
自由度は限定的
「フリーランス=自由度が高い」と思われがちですが、SES契約の場合は、プロジェクトに携わった勤務時間に対して報酬を受け取る形態となります。リモートワークが可能な案件も多くありますが、最近では出社を希望されるケースも増加しています。
中間マージンが発生する
エージェントや仲介会社が入るため、契約金額から一定のマージンが差し引かれます。
「クライアントが支払っている金額」と「自分の手取り」に差があるのは事実です。
成果より時間で評価される
請負契約のように「納品物」で評価されるのではなく、労働時間ベースでの契約です。
そのため、効率よく仕事を終えても報酬は変わらず、成果報酬型ではないことに不満を持つ方もいます。しかし、できることを率先して行うことで評価され、新しい案件に繋がることもあります。
SES契約の実態(体験談)
私自身、フリーランスになってからはSES契約で案件探しを続けています。
当時はスキルに自信がなく、案件探しには苦労しましたが、人脈やエージェントのサポートに助けられて継続的に案件を獲得できています。
特に、
- 案件によって業務内容や働き方が大きく異なる
- クライアントやチーム次第で働きやすさが変わる
といった「運の要素」もあり、必ずしも条件が理想通りになるわけではありません。
まとめ
SES契約はフリーランスが最も利用しやすい契約形態の一つで、案件数の豊富さ、安定収入、スキルアップといったメリットがあります。一方で、自由度の低さや中間マージンといったデメリットも理解しておく必要があります。
私自身、SES契約を通じて正社員時代には得られなかった貴重な経験と収入を得ることができました。また、エージェントの存在により、不安や心配ごとを相談できるため、メンタルケアの面でも大きな助けとなっています。
これからフリーランスを目指す方には、ぜひSES契約の実態を理解した上で、自分のキャリアプランに合った選択をしていただきたいと思います。
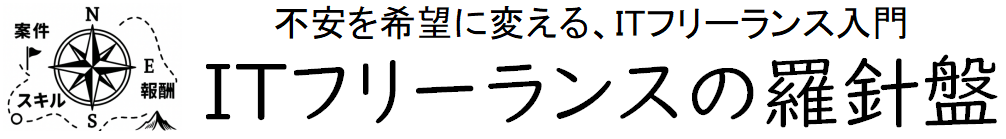
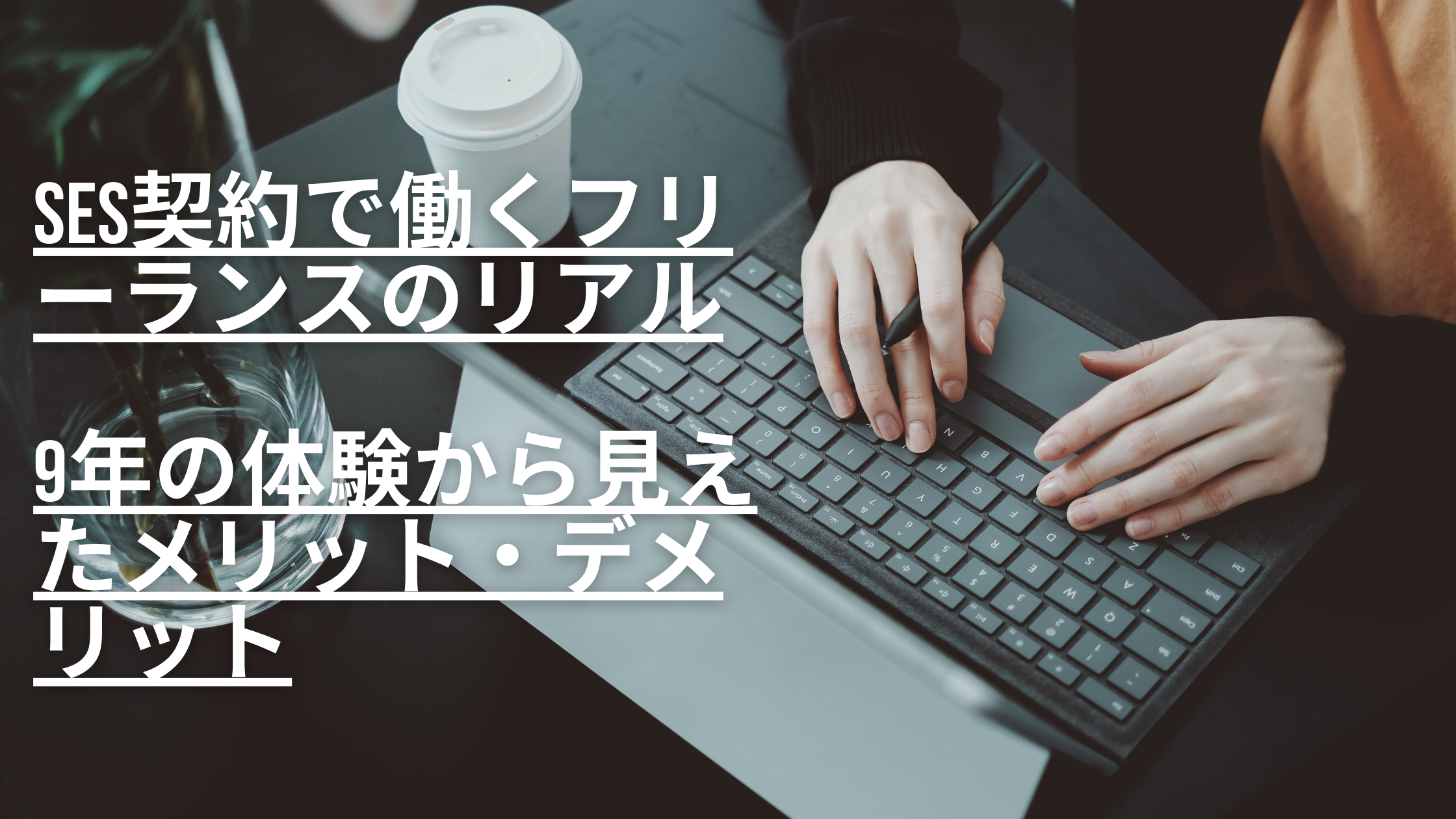
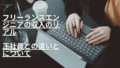
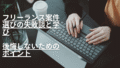
コメント